著者:丸山正樹さん
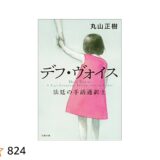
①本のかんたんな紹介
聴覚障害のある両親を持つ「CODA(コーダ)」として育った荒井尚人。
彼は手話を母国語のように使えることから、法廷の場で手話通訳士として働くことになる。
裁判という言葉の正確さが求められる場で、手話と日本語の間にあるズレや文化の違いに直面し、
「本当に伝えるべきことは何か」を模索していく。
②自分の考えや本への想い
本作は、聴覚障害者の両親を持ち、自らは健聴者として育った主人公(荒井尚人)が、法廷の場で手話通訳士を務める過程を描いている。そこに浮かび上がるのは、ろう文化と健常者の文化の違いであり、その溝の深さだ。
私たちは普段、「聞く」「話す」という行為を無意識に行っている。
しかし、ろう文化においては、手話が単なる翻訳言語ではなく、世界の感じ方や人との距離感を形づくる根幹的なコミュニケーション手段である。
日本語に比べ、手話はより直截的(※1)で視覚的な表現に富んでおり、そのリズムや言い回しは日本語に一対一で置き換えることができない。
裁判という、言葉の細部やニュアンスが人の運命を左右する場所において、この違いがいかに重大な意味を持つかが本作で繰り返し提示される。
聞こえる人々にとっての「正確な言葉」が、ろう者にとっては「意味の欠落した表現」になってしまうこともあるのだ。
尚人が法廷で被告人の手話を通訳する一場面が印象的だ。被告の発した手話は単純な言葉の羅列ではなく、身振りや表情、間の取り方に豊かな意味を含んでいる。
しかし、裁判官や弁護士は逐語訳(※2)を求める。尚人は忠実に訳すべきか、それとも文化的背景を踏まえて解釈を加えるべきか、苦悩する。そこで浮き彫りになるのは、通訳とは単なる言葉の置き換えではなく、異なる文化をつなぐ架け橋であるという事実だ。この場面から「伝えることの責任」とは何かを強く考えさせられた。
また本書には、健常者側の無意識の偏見も鋭く描かれている。「聞こえない人は不便だから助けるべきだ」という善意の裏に、相手を対等な存在として見ていない傲慢さが潜んでいる。
ろう文化は、音を必要とせずとも豊かな人間関係を築いてきた独自の文化であり、それを「欠落」とみなすのは健常者側の一方的な価値観にすぎない。
主人公が、ろう者と健常者のあいだで揺れ動きながらも両者を結びつけようとする姿に、私自身も「自分は他者の文化をどれほど尊重しているのか」と問い直された。
本作の実益性は大きい。まず、手話やろう文化に対する正しい理解を促してくれる点だ。
ニュースやドラマで手話が取り上げられることはあっても、文化的背景や細やかなニュアンスにまで触れる機会は少ない。
だが本書を読むことで、「手話=日本語の代替手段」という単純な理解が誤りであることに気づかされる。さらに、司法制度に潜む構造的な不平等も知ることができる。法廷の言語が常に日本語であり、そこに合わせられない人々が不利な立場に追い込まれる現実は、社会全体の縮図でもある。
つまり本作は、ろう者の問題を通じて「多様性をどう保障するか」という普遍的な課題を突きつけてくるのだ。
※1直截的:物事を遠回しではなくはっきりと言う様子のこと
※2逐語訳:原文の一語一語を忠実に解釈・翻訳すること
③まとめ
ろう文化と健常者文化の差異を鮮明に描き出す社会派小説である。
手話は単なる日本語の代替手段ではなく、独自の表現体系をもつ言語であり、その文化的背景を無視した逐語的通訳は司法の場で誤解や不利益を生む危険を孕む。
主人公・荒井尚人が通訳士として直面する葛藤は、言葉を媒介とする権力構造とマイノリティの置かれる不平等を可視化する。
本作の意義は、手話やろう文化への理解を促す点にとどまらず、多様性を尊重する社会のあり方を問う点にある。
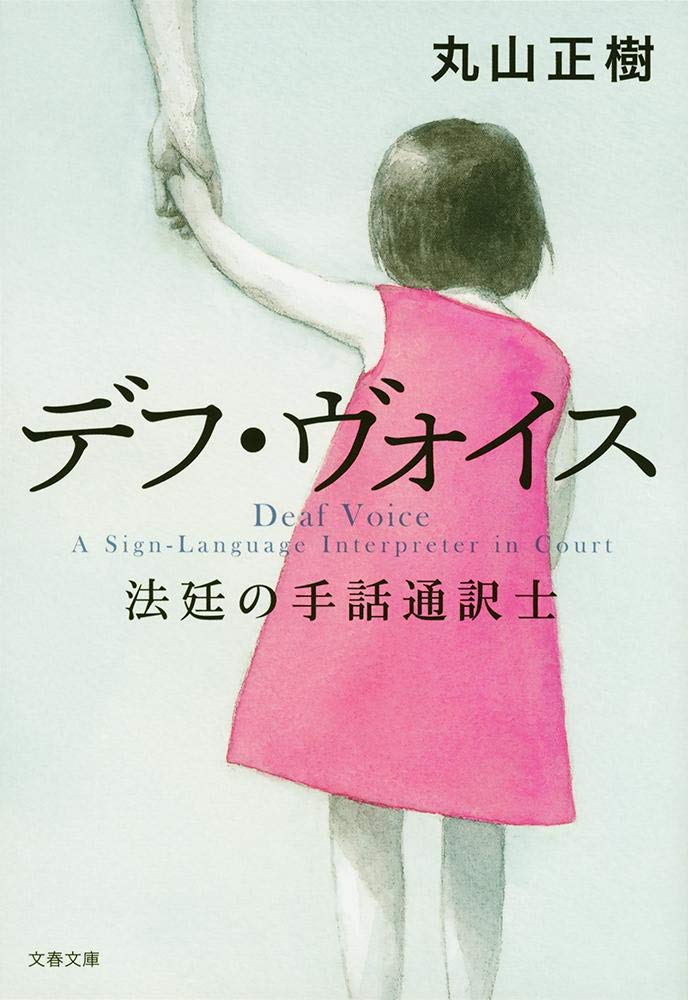

コメント