著者:森見登美彦さん
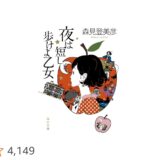
①本のかんたんな紹介
主人公は京都の大学に通う「先輩」。彼は同じサークルの後輩「黒髪の乙女」に恋心を抱いているが、告白する勇気がなく「なるべく目立たず彼女に気づかれる」作戦を続けている。一方、乙女は天真爛漫で自由奔放な性格。酒場での飲み比べ、下鴨神社の古本市、大学の学園祭など、京都の街を舞台に奇想天外な出来事に次々と巻き込まれていく。物語は春夏秋冬をめぐり、先輩の片思いと乙女の成長が描かれる。現実と幻想が入り混じるユーモラスな筆致で、青春の勢いと恋のもどかしさを表現した作品である。
②自分の考えや本への想い
この本の第一印象は青春の勢いと不思議さをこれほどユーモラスに描いた小説は珍しいだった。
物語は京都を舞台に、黒髪の乙女と彼女に恋する「先輩」の視点で進んでいく。現実と幻想が混ざり合い、奇妙な事件や人々に出会いながら、二人の関係は少しずつ近づいていく。
印象に残ったのは、やはり先斗町の酒場で乙女が大人たちと酒を飲み比べる場面である。次々と杯を飲み干していく乙女の姿は破天荒で、まるで夜の街そのものを味方につけているかのようだった。普通なら無茶な行為に見えるのに、彼女の前向きさと底なしの明るさによって、それがむしろ祝祭的な出来事に変わってしまう。読んでいる私まで楽しくなり、若さの勢いとはこういうものかと圧倒された。このシーンを通じて、作者は「青春の力は理屈では測れない」ということを伝えているように思う。
また、本書には実際に役立つ学びもあった。京都の古本市や先斗町の街並み、大学の学園祭などが描かれており、読者は現実の京都を訪れるときに新しい視点を持つことができるだろう。
さらに先輩の「ナカメ作戦」に見られるように、人に近づこうとするぎこちなさや、告白できないもどかしさは、誰もが心当たりのある感情である。小説を通して、自分自身の不器用さを笑い飛ばし、肯定できる気持ちになれた点は大きな実益だった。
そして何より強く心に残ったのは、森見登美彦さんの独特な文体である。古風な言い回しを使いながらもユーモラスで軽やかであり、堅苦しさよりもリズムの楽しさを感じる。
京都の街がまるで生き物のように描かれることで、物語の舞台そのものがキャラクターとして存在感を放っていた。現実と幻想の境目が曖昧になり、読んでいる自分までも京都の夜に迷い込んでしまったような感覚にとらわれた。
青春の勢いと不器用さを肯定し、同時に人生を少し楽しく眺める視点を与えてくれる物語である。先輩の必死な追いかけ方も、乙女の自由奔放な歩み方も、どちらも間違いではなく、それぞれが青春の形なのだと教えてくれる。
青春をすでに過ぎた人にも、今まさに青春の最中にいる人にも、それぞれの立場から共感や発見を与えてくれるだろう。私はこの物語を通して、「自分もまた自由に歩いていいのだ」と背中を押されたような気がする。
③まとめ
京都の夜を舞台に、乙女と先輩の奇想天外な青春が繰り広げられる。酒場、古本市、学園祭。
日常が幻想に変わる世界で、もどかしくも可笑しい恋の物語。読むたびに笑いと胸の高鳴りを届ける、唯一無二の青春小説。

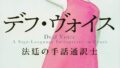
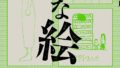
コメント